DeepSeek(ディープシーク)とジェボンズの逆説の関係とは?DeepSeekが米国株式市場にもたらす影響を徹底解説!
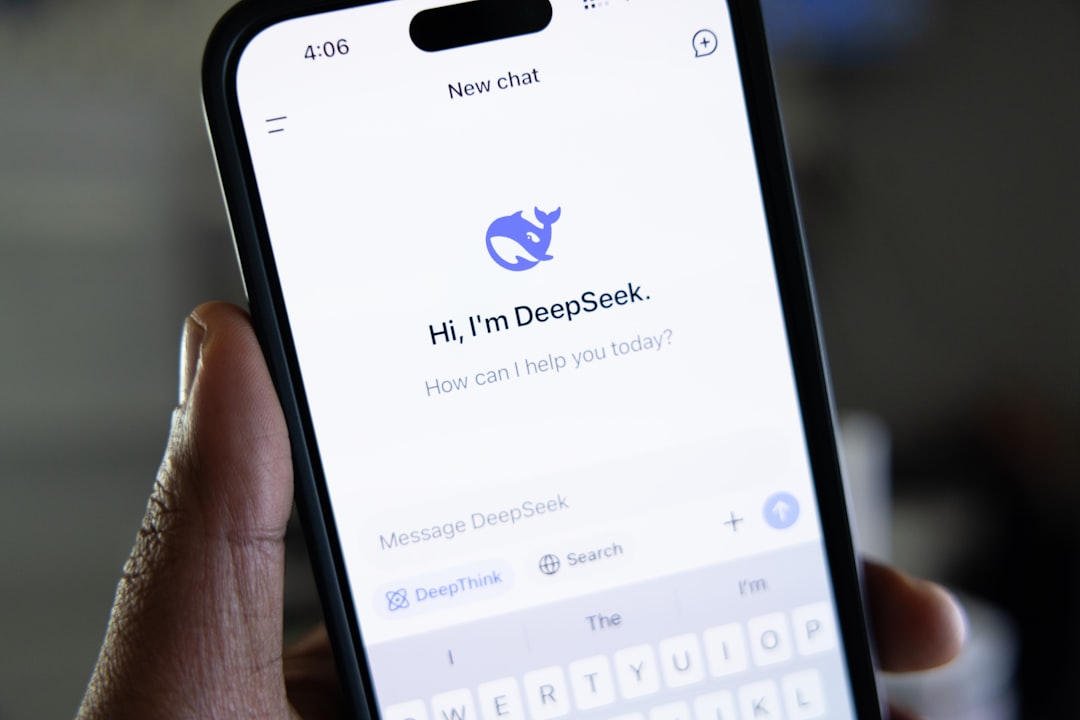
 ダグラス・ オローリン
ダグラス・ オローリン- 本稿では、DeepSeek(ディープシーク)とジェボンズの逆説(ジェボンズのパラドックス)の関係の分析を通じて、DeepSeekが米国株式市場にもたらす影響を詳しく解説していきます。
- DeepSeekは、中国のAI企業で、数理推論やコーディングに強みを持つオープンソースの大規模言語モデル(LLM)を開発しており、最新の「DeepSeek-V3」や「DeepSeek-R1」などのモデルで注目を集めています。
- AIインフラ投資の減速が懸念される中、技術の進化により「新たなインフラが不要」とする見方が強まる一方で、ジェボンズの逆説に基づく強気シナリオでは、AIのコスト低下が需要を拡大させる可能性を指摘しています。
- 市場は過熱しており、短期的には価格変動が激しくなる可能性があるが、長期的にはAI関連銘柄の成長が続くと考えられ、特に中国の動向が注目しています。
DeepSeek(ディープシーク)とは?
私のお気に入りの市場の格言のひとつに、「物語は価格に従う」というものがあります。DeepSeek(ディープシーク)のケースでは、まさにこの言葉が当てはまります。本稿では、DeepSeekの概要をまとめるとともに、現在の「ムードのサイクル」のどの段階にあるのかについて詳しくお話しします。DeepSeekが面白いのは、わずか1か月前の状況とあまりにも対照的だからです。
まず、
DeepSeekは、中国・浙江省杭州市に拠点を置くAI企業で、2023年に設立されました。同社はオープンソースの大規模言語モデル(LLM)および生成AIプラットフォームの開発を行っており、特に数理推論やコーディング能力に強みを持っています。
2024年12月に発表された「DeepSeek-V3」モデルは、Mixture-of-Experts(MoE)アーキテクチャを採用し、6710億のパラメータを持ちながら効率的なトレーニングと推論を実現しています。
さらに、2025年1月には「DeepSeek-R1」や「Janus-Pro」といったモデルを公開し、AI業界で急速に注目を集めています。 DeepSeekのAIモデルは、開発や運用コストを大幅に抑えつつ、高い性能を発揮しており、特に数理推論やコーディング能力において優れた成果を示しています。
一方で、1か月前、NeurIPSの時期においては、「事前学習のスケーリング則が鈍化している」というのが支配的な見方でした。そのため、AIインフラへの投資は鈍化し、新たな設備への追加投資はリターンに見合わないと考えられていました。
しかし、SemiAnalysisは、その見解が誤りである理由を見事に説明しました。皮肉なことに、強化学習やアーキテクチャの進化が続くことが、その主な要因のひとつでした。事前学習のペースが落ちたことで、GPUの需要は「終わった」と考えられていたのです。
そして現在、DeepSeekは1月20日(2025年)に推論モデルを発表し、さらに12月26日(2024年)にはv3という小型モデルをリリースしました。この動向を注視していた人なら、「知能は測定不能なほど安価になる」というコンセプトがX上で話題になっていたことを知っているでしょう。しかし、金曜日から週末にかけて、この物語はさらに劇的な方向へと変わりました。
ここで注目すべきなのは、どちらの議論もインフラ投資にとって「ネガティブな要素」として捉えられている点です。しかし、後者は前者を覆す内容になっています。つまり、「アルゴリズムの進化があまりに進んだため、新たなインフラはもう必要ない」という見方が強まっているのです。技術は進歩したものの、需要は損なわれている。しかし、現実はこの2つの極端な意見のどちらかに完全に当てはまるわけではなく、GPU需要の議論としては不完全です。市場が前の四半期に熱望していた中国企業のアルゴリズムの進歩が、突然「終わりを迎えた」とは到底考えられません。
実際のところ、市場は過熱しており、何かのきっかけで動揺しやすい状況にあります。ありきたりな表現ですが、「ミスター・マーケットは双極性を持っている」と言わざるを得ません。これは、AI企業が乗り越えなければならない最新の「壁」にすぎないのです。ここからは、強気派と弱気派の議論を整理し、私の見解を述べていきたいと思います。
DeepSeek(ディープシーク)とジェボンズの逆説(強気シナリオ)
ジェボンズの逆説(ジェボンズのパラドックス:Jevons paradox)というフレーズは初めて聞くかもしれませんが、今日がまさに一般的な言葉として広まる日になるでしょう。現在の検索トレンドを見ても明らかです。おそらくArkk Investのキャシー氏がこの概念を広めたのだと思いますが、今日は強気派のスローガンになっています。

(出所:Google Trends)
では、「ジェボンズの逆説」とは何でしょうか? これは基本的に、「技術の進歩によって特定の財の価格が下がると、逆説的にその財の需要が増える」という観察結果のことです。いくつかの代表的な例がありますが、私が最も興味深いと思うのはトランジスタです。
トランジスタの価格は50年間、毎年安くなりました。しかし、価格が下がるにつれて必要な量が減るどころか、微細化の影響を考慮しても、むしろ使用量は大幅に増加しました。たとえば、飛行機の運賃が数千ドルから数十ドルに下がったとしたら、私たちはもっと頻繁に飛行機を利用するようになるでしょう。
図:価格が100ドルから80ドルに下がることで、需要量が10から14に増加する浅い需要曲線

(出所:PNGEgg)
考え方としては、「価格が安くなれば、それをより多く使うようになる」というもので、これは弾力的な需要の定義そのものであり、ジェボンズの逆説が適用される典型的なケースです。
では、これをAIの文脈で考えてみましょう。これはWebWalkerQA(特に有用な論文ではありません)が挙げた例ですが、2つのエージェント型AIが協力してウェブサイトを検索し、より良い情報を提供するというものです。

(出所:Marktechpost Media)
もしエージェントのコストが下がったら、なぜ2つで止める必要があるのでしょうか? ある友人が、「あなたのスマートコーヒーマシンが毎日最高のコーヒーを淹れるために100万のアインシュタインを雇えるとしたら?」と冗談を言っていました。知能のコストが下がるほど、世界の重要な課題に対して、 brute-force(計算資源を総動員する手法)による知能の投入量は増えるでしょう。
コストが劇的に低下する世界では、効率化が進むどころか、むしろリソースの投入量が増えるのが現実です。
これこそが、ジェボンズの逆説を強気シナリオとして捉える要点であり、長期的に確実に起こる現象であるように見えます。月面着陸には約16,000個のトランジスタが必要でしたが、今では同じ数のトランジスタでどんな最新のアプリケーションでも動かせるでしょう。価格が下がったものはより多く使われ、皮肉なことに需要が爆発的に増加するのです。
DeepSeek(ディープシーク)と供給が需要を上回る問題とタイムライン
ひとつ小さな問題があります。これは最近の資本サイクルに関する記事でも書いたことですが、リードタイムとラグタイムの影響によって市場に歪みが生じ、非常に極端なシナリオが生まれることがあります。ジェボンズの逆説が正しいかどうかという問題ではなく、「私たちは本当にもっと使うようになるのか?」ではなく、タイミングの問題が重要になってきます。
この点に関しては、直近執筆した下記のレポートでも触れておりますので、併せてご覧いただければと思います。


もし90%性能が向上したモデルの「デフレーター効果」が、需要増加を大幅に上回るとどうなるでしょうか? これについては、DWDM(高密度波長分割多重)の事例が参考になります。DWDMは光ファイバーの供給を大幅に増加させました。その結果、ジェボンズの逆説が長期的には100%正しいとされる一方で、2001年に敷設された光ファイバーの97%が未使用のままだったのです。今日ではそのほとんどが使用されていますが、このようにジェボンズの逆説が長期的には正しくても、短期的には現実と大きく乖離することがあります。
これは、供給が需要を大幅に上回るケースとして、市場が今まさに直面している問題です。最終的な価値(terminal value)は関係者全員にとって受け入れ可能なものになるかもしれませんが、短期的なギャップが問題になるのです。
このケースにおける弱気シナリオ(ベアケース)は、ジェボンズの逆説は確かに成立するが、短期的には供給が需要を圧倒するため、供給の急増が長期的な需要を上回ってしまうというものです。
しかし、現実はいつも最悪の想定ほど悪くもなく、夢見たほど良くもないものです。
DeepSeek(ディープシーク)の発表を受けての私の見解
正直なところ、この市場は売りの口実を探しているように見えます。スケーリング則に関する議論は確かに重要でしたが、現在では明らかに克服されています。それなのに、それすら「悪いこと」だとされている状況です。これは、まさに市場が弱気派の主張を克服しつつある証拠です。いわゆる「ウォール・オブ・ウォーリー(懸念の壁)」ですね。
この騒ぎが過剰反応だと感じる理由は、DeepSeekが発表されて数日しか経っていないのに、知人から突然メッセージが届くことです。それに、Gemini Flash Thinking 2.0が登場し、さらに低コスト化が進んでいます。

(出所:@daniel_mac8)
しかし、これはアルファベット(GOOG)の発表なので、大きなニュースにはなりにくいのです。ジェボンズの逆説は、「世界中がGPUを求めている」という前提があれば確実に機能します。そして、今まさにその状況です。
実際、各社の発注状況や、大手研究機関でのレート制限の実施、さらにはD社がサービスの提供を抑制している事実などが、市場の現状を物語っています。
計算資源(コンピュート)は依然として最大のボトルネックであり、少しでも緩和されることは市場にとってプラスなのです。
DeepSeek(ディープシーク)の発表後に私が本当に懸念していること(価格変動と市場心理)
ここからが私が本当に懸念しているポイントです。市場心理ほど価格の影響を受けやすいものはありません。
現在、サティア・ナデラ氏はAI分野で最大の投資家でありながら、私の見解では最も投資を抑制しつつある人物でもあります。彼は「800億ドルは確保済み」ですが、来年の設備投資(CapEx)の意欲こそが最も重要な焦点になるでしょう。
もちろん、市場がバブル気味であることは否定しません。比較的無名な研究機関の発表が、世界最大の企業の株価を1日で16%下落させたという事実は、AI投資熱の過熱ぶりを物語っています。この点は少し懸念すべき要素です。

(出所:Bloomberg)
一方で、急激な下落(ドローダウン)は起こり得るものです。 これは1990年代のシスコシステムズ(CSCO)の株価推移ですが、個人的にはエヌビディア(NVDA)の動きに最も近いアナロジーだと思います。しかし、まだ終わったわけではありません。市場の熱狂が続く限り、踊り続けるのが賢明であると考えています。
私はDeepSeekの影響は長期的には大した問題にはならないと考えています。しかし、エヌビディアの株価は現在約20%下落しており、更なる下落もあり得ます。とはいえ、30%の下落(昨年8月の調整時と同程度の水準)になれば、私は積極的に買い向かうでしょう。結論として、強気派と弱気派の議論では、私はかなり強気寄りのスタンスを取っています。
ただし、誤解しないでください。Stargate Projectの進展、そしてAI関連銘柄への市場の資金集中を考慮すると、我々は「終わりの始まり」の段階にいると言えます。この「終わり」が数年続く可能性は十分ありますが、米中間のAI競争が本格化することは避けられないでしょう。 そして、ついに中国からの最初の反撃が見え始めました。
「面白い時代に生きることができますように」——まさに今、その真っ只中にいるのかもしれません。
また、私は半導体&テクノロジー銘柄に関するレポートを毎週複数執筆しており、私のプロフィール上にてフォローをしていただくと、最新のレポートがリリースされる度にリアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることができます。
さらに、その他のアナリストも詳細な分析レポートを日々執筆しており、インベストリンゴのプラットフォーム上では「毎月約100件、年間で1000件以上」のレポートを提供しております。
そこで、私の半導体&テクノロジー銘柄に関する最新レポートを見逃さないために、是非、フォローしていただければと思います!
加えて、足元では、下記の6の章から構成される長編レポートにおいて、2025年に注目の半導体関連銘柄に関して詳しく解説しておりますので、こちらも併せてご覧いただければと思います。
アナリスト紹介:ダグラス・ オローリン / CFA
📍半導体&テクノロジー担当

オローリン氏のその他の半導体&テクノロジー銘柄のレポートに関心がございましたら、こちらのリンクより、オローリン氏のプロフィールページにてご覧いただければと思います。

インベストリンゴでは、弊社のアナリストが「高配当銘柄」から「AIや半導体関連のテクノロジー銘柄」まで、米国株個別企業に関する分析を日々日本語でアップデートしております。さらに、インベストリンゴのレポート上でカバーされている米国、及び、外国企業数は「250銘柄以上」(対象銘柄リストはこちら)となっております。米国株式市場に関心のある方は、是非、弊社プラットフォームより詳細な分析レポートをご覧いただければと思います。