【半導体】インテル(INTC)業績悪化理由の真相とは?UBSグローバルテクノロジーカンファレンスにおける同社役員の発言を徹底分析!
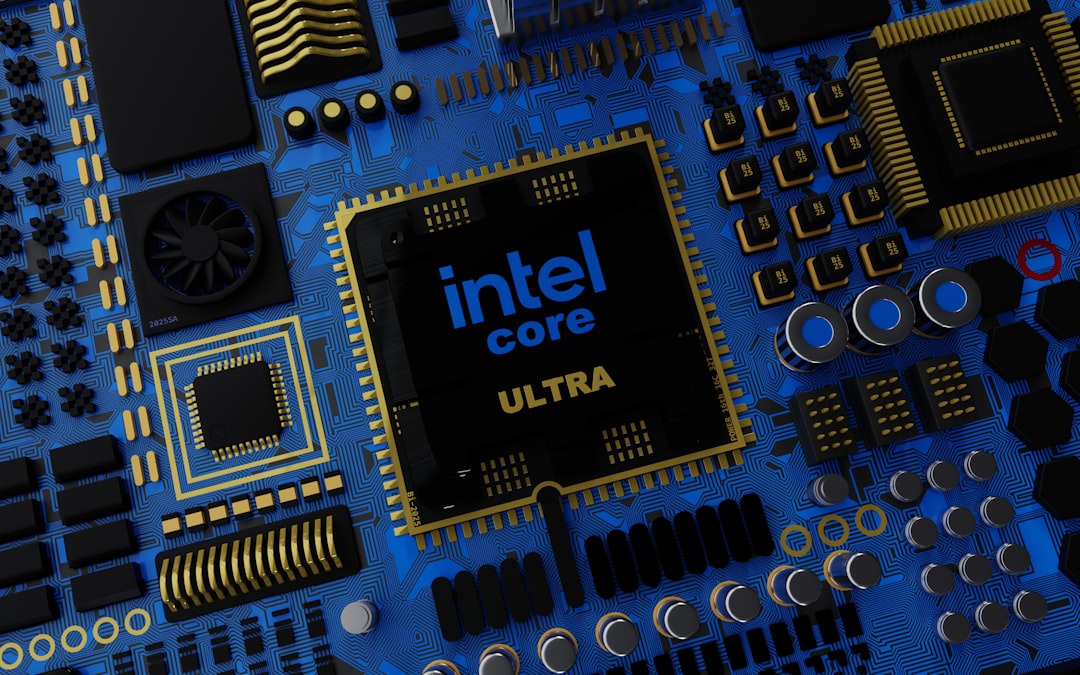
 ウィリアム・ キーティング
ウィリアム・ キーティング- 本稿では、注目の米国半導体銘柄であるインテル(INTC)の足元の業績悪化理由を探るべく、UBSグローバルテクノロジーカンファレンスにおける同社役員の発言の分析を通じて、今後の見通しと将来性を詳しく解説していきます。
- インテルのゲルシンガー元CEO退任後、同社のCFOとIFS部門のGMがUBSのカンファレンスでIDM 2.0戦略の継続性や資本投資方針について詳細を説明しています。
- ゲルシンガー氏の退任理由は個人的な事情に起因し、取締役会との意見の相違や成長率の過大評価が背景にある可能性が指摘されています。
- そして、インテルは設備投資への慎重なアプローチを採りつつ、ファウンドリとプロダクト部門の成功を両立させる方針を維持しています。
インテル(INTC)のUBSグローバルテクノロジーカンファレンスにおける発言とは?
インテル(INTC)のゲルシンガー氏が突然退任してからわずか2日後に開催されたUBSグローバルテクノロジーカンファレンスでのファイヤサイドチャットは、非常に注目を集めました。
このセッションには、インテルのCFOであるデビッド・ジンズナー氏と、新たにIFS(インテルファウンドリサービス)のGMに就任したナガ・チャンドラセカラン氏が登壇しました。
少し背景を説明すると、チャンドラセカラン氏は2024年8月にインテルに加わり、ファウンドリ製造およびサプライチェーンの責任者としてケイバン・エスファルジャニ氏の後任を務めています。

(日本語訳)カリフォルニア州サンタクララ、2024年7月25日 – インテルは本日、ナガ・チャンドラセカラン博士がチーフグローバルオペレーションズオフィサー、エグゼクティブバイスプレジデント、そしてファウンドリ製造およびサプライチェーン部門のゼネラルマネージャーに就任したことを発表しました。チャンドラセカラン博士は、これまでマイクロンでテクノロジー開発部門のシニアバイスプレジデントを務めていました。彼はインテルの経営幹部チームの一員となり、CEOであるパット・ゲルシンガー氏に直属します。
(出所:インテルのHP)
インテルに入社する前、彼はマイクロン・テクノロジー(MU)で長い間際立ったキャリアを築いていました。
(原文)During more than 20 years at Micron, Chandrasekaran served in various senior leadership roles. Most recently, he led Micron’s global technology development and engineering efforts related to the scaling of current memory technologies, advanced packaging technology and emerging technology solutions. Previously, he served as Micron’s senior vice president of Process R&D and Operations. His experience spans the breadth of semiconductor manufacturing and R&D, including process and equipment development, device technology, mask technology and more
(日本語訳)マイクロンでの20年以上にわたるキャリアの中で、チャンドラセカラン氏は数々の上級管理職を歴任しました。直近では、最新のメモリ技術のスケーリング、先進的なパッケージング技術、新興技術ソリューションに関するグローバルな技術開発およびエンジニアリングを指揮していました。それ以前には、プロセス研究開発(R&D)およびオペレーションの上級副社長を務め、半導体製造や研究開発の幅広い分野にわたる経験を積みました。その専門性は、プロセスや装置の開発、デバイス技術、マスク技術など、多岐にわたります。
インテルに入社して間もないため、チャンドラセカラン氏が議論に大きく貢献するとは正直思っていませんでした。
しかし、それは私の誤算でした。
彼は、新しい役職に就いてまだ数カ月にもかかわらず、直面している課題について非常に率直で正直な評価を述べてくれました。
今回のイベントでの私たちの主な関心は、ゲルシンガー氏の突然の退任理由について何らかの手がかりを得ること、そしてインテルのIDM 2.0戦略に変化があるかどうかを見極めることでした。
退任理由に関して最も近づけた手がかりは、ジンズナー氏が「なぜ取締役会がプロダクトグループにより注力しているのか、そしてなぜゲルシンガー氏がその役割に適していなかったのか」という質問に対して述べた次のコメントでした。
(原文)Question: there's a question of who like if the product business is what's important to the board now I mean Pat knew the products better than anybody so so there is some confusion I think among some investors if that's the emphasis for the board that seemed like the perfect guy
(日本語訳)質問:「もし取締役会にとってプロダクトビジネスが今の重要課題だとしたら、パット・ゲルシンガー氏は製品のことを誰よりもよく知っていたはずです。そのため、取締役会がそこに重きを置いているのであれば、彼が最適な人材だったように思えるので、一部の投資家の間で混乱が生じているように感じます。」
(原文)Answer: Now I wouldn't read into the fact that the board wants to focus on that make sure we you know build out the products business and continue to execute there while you know standing up a foundry business as something related to Pat and the board deciding that now is the right time that was you know for personal reasons specific to Pat and the board.
(日本語訳)回答:「取締役会がプロダクトビジネスの拡大や継続的な実行、さらにファウンドリ事業の立ち上げに注力したいと考えていることを、パット氏や取締役会との間の決定に関連付けて考える必要はありません。今回のタイミングは、あくまでパット氏個人の事情によるものであり、それに基づいて取締役会とパット氏が判断した結果です。」
ここでの示唆は、ゲルシンガー氏の退任がIDM 2.0戦略そのものとは直接関係しておらず、むしろ彼と取締役会との間で生じた個人的な意見の対立によるものだということです。
通話の記録を読み進めると、その対立が何をめぐるものだったのかが徐々に見えてきます。
それでは、さらに詳しく見ていきましょう。
また、私のプロフィール上にて、私をフォローしていただければ、最新のレポートがリリースされる度にリアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることが出来ます。
私の半導体に関するレポートに関心がございましたら、最新のレポートを見逃さないために、是非、フォローしていただければと思います。
ゲルシンガー氏の退任が報じられた際、インテル(INTC)の財務状況に関する予期せぬ問題、例えば今四半期の業績見通しを達成できない可能性などが原因ではないかと考えました。
しかし、ジンズナー氏の話によれば、どうやらそうではないようです。
(原文)Yeah we typically don't provide updates and we still have another month to go, that's a lot of wood to chop so we stand by the guidance that we gave at earnings and more updates obviously when we do our earnings at the end of January which I'll be doing double duty on it sounds like.
(日本語訳)通常、途中で見通しを更新することはありませんし、まだ1カ月も残っています。やるべきことはたくさんありますので、これまでの決算発表で示した見通しを引き続き維持します。詳細については、1月末の決算発表時にお知らせします。その際には、私が複数の役割を兼任することになりそうです。
そして、IDM 2.0の基本戦略については、これまで通り変更はありません。
(原文)Yeah it shouldn’t. I mean the board was pretty clear that the core strategy remains intact. We still want to be a world-class foundry, we want to be the western provider of leading edge silicon to customers. That remains our goal.
(日本語訳)そうですね、変わることはありません。取締役会は基本戦略が引き続き維持されることを明確に示しています。私たちは引き続き、世界トップクラスのファウンドリを目指し、最先端のシリコンを顧客に提供する西側の主要プロバイダーであり続けることを目標としています。それが私たちの変わらない方針です。
また、取締役会がMJ(ミシェル・ジョンストン・ホルツハウス氏)をプロダクトグループの責任者とする新たな役職を設けた理由は何でしょうか?
(原文)but we also understand that it's important for the number one customer of foundry to be successful in order for foundry to be successful. So the board wants to also put emphasis on execution around the product side of the business to make sure that the foundry business remains successful.
(日本語訳)ファウンドリ事業が成功するためには、最大の顧客であるプロダクト部門が成功することが重要だと理解しています。そのため、取締役会はファウンドリ事業の成功を支えるため、プロダクト部門の実行力にも重点を置くことを望んでいます。
ここから推測されるのは、取締役会がこれまでプロダクト部門の実行力への注力が十分ではないと感じ、その状況を改善する役割をMJに任せたということです。
それでも、この動きにはやや違和感があります。
暫定的な共同CEOとして、プロダクト部門を彼女の管轄下に置くことは新しい役職を作らなくても可能だったはずです。
おそらく、これはインテルをファウンドリとプロダクトという2つの論理的な事業部門に分割する次のステップに過ぎないのではないでしょうか。
取締役会がジンズナー氏に送ったメッセージ、そしておそらくゲルシンガー氏の解任を決断した背景について、私たちは次のようなことを知りました。
(原文)I'd say the one thing that has definitely come out of the way the boards thinking about this is they do recognize and have pushed us that hey we've made a lot of investments from a capital perspective in foundry and we need to start seeing some incremental ROIC on those investments and so and that's what we're committed to do. That's going to be one of my major focuses definitely while I’m CFO and interim co-CEO.
(日本語訳)取締役会の考え方で明らかになったのは、これまでファウンドリに多額の資本投資を行ってきたことを取締役会自身も認識しており、その投資に対して徐々にROIC(投下資本利益率)を示す必要があると強く求めている点です。そして、それを実現することが私たちの責務です。これは、私がCFO兼暫定共同CEOを務める間、間違いなく最重要課題の一つになるでしょう。
これは、ゲルシンガー氏が進めてきた再建プロセスの遅さに対する取締役会の不満を示しているようです。
議論を通じて、この件に関連し取締役会が抱えている課題について、いくつか明確なヒントが得られました。
(原文)we're really moving toward the model where we're going to assume a relatively GDP type of growth rate for the business.
(日本語訳)私たちは、事業の成長率を比較的GDPに近い水準で想定するモデルへと移行しつつあります。
(原文)it's not the way Intel necessarily thought about capital investment in the past and so what we should see is incrementally better ROIC for capital dollars that get deployed because we're just you know way more conservative around how we roll out capital.
(日本語訳)これは、インテルがこれまで資本投資を考えていた方法とは必ずしも同じではありません。そのため、資本を投入する際にはこれまで以上に慎重なアプローチを取ることで、結果的に投下資本利益率(ROIC)が徐々に改善されることが期待できるでしょう。
ここで浮かび上がるのは、設備投資(CapEx)に対してこれまで以上に慎重なアプローチを取る姿勢です。
事業の成長率をGDP並みと想定する方針は、ゲルシンガー氏の「工場を建てれば顧客が集まる」というアプローチとは大きく異なります。
この点が、私たちが最近のレポートで指摘した内容と正確に一致しているのは非常に興味深いことです。
(原文)When the board reviewed and approved his IDM 2.0 strategy, in particular the massive fab build out component, they apparently forgot to ask two simple questions. One, why do we need so much capacity? Two, how are we going to pay for it? The answers to both questions would have been quite simple. No, you don’t need so much capacity and even if you did, we can’t afford it.
(日本語訳)取締役会がゲルシンガー氏のIDM 2.0戦略、特に大規模な工場建設計画を検討し承認した際、どうやら2つの基本的な質問を見落としていたようです。1つ目は「なぜこれほど多くの生産能力が必要なのか?」そして2つ目は「その資金をどうやって調達するのか?」という問いです。この2つの質問への答えは至って明白だったはずです。「そんなに多くの生産能力は必要ないし、仮に必要だとしても、それを賄う資金はない」という結論です。
ジンズナー氏は、自身とゲルシンガー氏が将来の生産能力の需要を過大評価していた可能性について、率直に認める発言をしました。
(原文)You know we have been investing at a rate that assumes a rate of growth for our first customer that's higher than probably we should have assumed. Clearly you know in the like 21 22 era that will for sure that was happening because we thought PC volumes we're gonna go up not down from you know kind of 21 levels so that's clearly is a big change for us in terms of the mentality.
(日本語訳)正直なところ、最優先の顧客に対して、実際よりも高い成長率を前提として投資を進めていました。特に2021年から2022年の時期にはその傾向が顕著で、当時はPCの出荷台数が2021年の水準から減るのではなく増えると考えていたのです。この認識の変化は、私たちの考え方にとって大きな転換点となっています。
正直、2021年のPC出荷台数がそのまま維持されると信じていたこと自体、私には全く理解できません。
以下のグラフを見ると、過去18年間のPC出荷台数の推移が分かります。
2010年から2012年のピークを境に、2019年まで非常に明確な下降トレンドが続いていました。
2020年にはわずかな増加が見られ、その後2021年には明確な理由で異常な急増が起きました。
年間PC出荷台数(ガートナー:2006年~2023年)

(出所:Gartner社のデータを基に筆者作成)
2021年の出荷台数が2022年以降も続くと信じるのは完全に誤った考えですが、その信念に基づいて数百億ドルもの設備投資を決断するのは、さらに深刻な問題です。
これを実行したのがインテルです。
当然ながら、ここには取締役会の責任があります。
ゲルシンガー氏がこれほど大規模な投資を行うには、取締役会の明確な承認が必要だったはずです。
私の考えでは、取締役会には多くの説明責任があると言わざるを得ません……。
次章では、注力製品である18Aに関する発言の分析を通じて、インテルの将来性を詳しく解説していきます。
※続きは「【半導体】インテル(INTC)の株価はなぜ下落?18AはHPC用途に適している一方、モバイル市場や幅広いエコシステムには対応不可?」をご覧ください。


その他のインテル(INTC)に関するレポートに関心がございましたら、是非、こちらのリンクより、インテルのページにアクセスしていただければと思います。
また、私のプロフィール上にて、私をフォローしていただければ、最新のレポートがリリースされる度にリアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることが出来ます。
私の半導体に関するレポートに関心がございましたら、最新のレポートを見逃さないために、是非、フォローしていただければと思います。
加えて、足元では、下記のレポートにおいて、インテルの次期CEOが直面する課題に関して詳しく解説しております。
次期CEOが直面する課題


また、直近では、弊社の半導体セクターアナリストであるダグラス・ オローリン氏が、5つの章から成る分析レポートにおいて、直近で話題となっているインテルのパット・ゲルシンガー元CEOの退任の理由から同社の将来性まで詳細な分析を提供しております。


インテルに対する理解を深めるために、是非、これらのレポートも併せてご覧いただければと思います。
アナリスト紹介:ウィリアム・キーティング
📍半導体&テクノロジー担当
.1735305551530.jpg)
キーティング氏のその他の半導体関連銘柄のレポートに関心がございましたら、是非、こちらのリンクより、キーティング氏のプロフィールページにアクセスしていただければと思います。
