インテル(INTC)が買収されたら株価はどうなる?インテルの買収先はどこ?足元で流れる観測とその可能性を徹底分析!
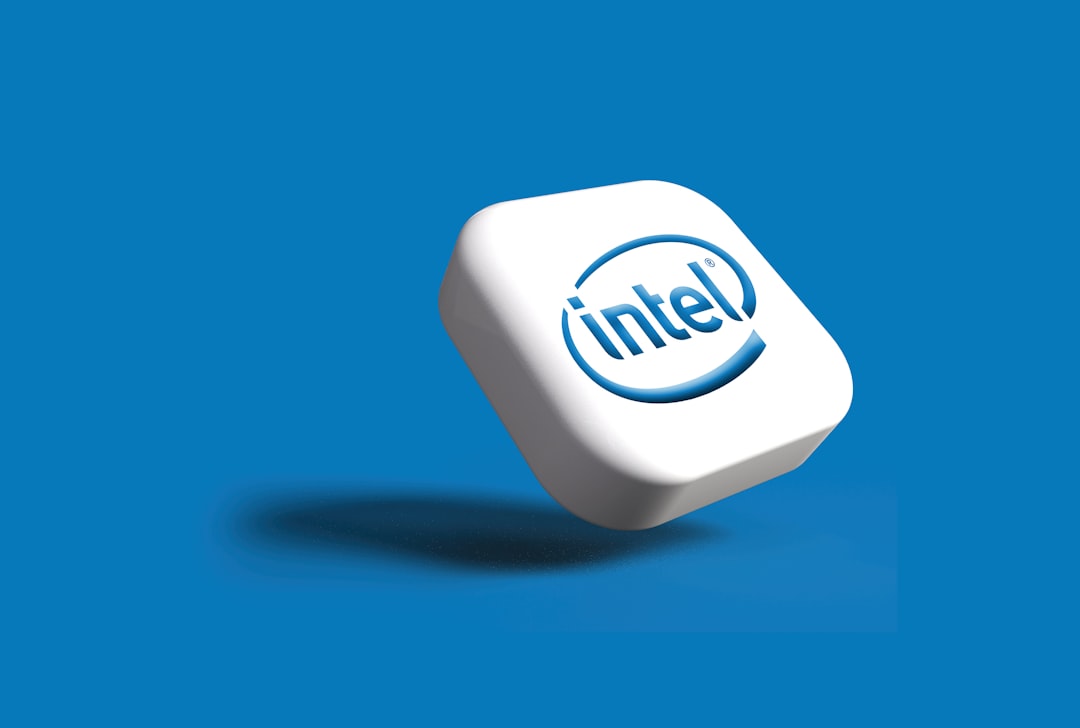
 ウィリアム・ キーティング
ウィリアム・ キーティング- 本稿では、「インテル(INTC)が買収されたら株価はどうなるのか?」、「インテルの買収先はどこ?」といった疑問に答えるべく、足元で流れている同社を取り巻く観測とその可能性に関して詳しく解説していきます。
- インテルは、ブロードコム(AVGO)によるチップ設計部門の買収やTSMC(TSM)による工場取得の可能性が報じられており、同社の将来を巡る議論が活発化しています。
- インテルは技術的な製造リーダーシップの喪失や設計面での遅れにより、TSMCへの依存が増加し、収益性の低下や市場シェアの減少といった課題に直面しています。
- インテル・ファウンドリー・サービス(IFS)の分離やスピンアウトの可能性が示唆されていますが、SCIP契約やCHIPs法の規制が絡むため、実現には長い時間と複雑な手続きが必要となる見込みです。
インテル(INTC)の最新の買収報道に関して
インテル(INTC)の将来をめぐる議論が、ここ一週間でかつてないほど激化しています。通常、信頼できるとされる報道機関からは、ブロードコム(AVGO)がインテルのチップ設計部門の買収を検討している可能性がある(Bloomberg)という報道や、TSMC(TSM)がインテルの工場を狙っている(Wall Street Journal)といった報道が相次いでいます。それに加えて、ブロードコムが仕掛けたとされる動きも伝えられています。
ブロードコムとTSMC、インテルの分割案を検討か
設計事業に関心のブロードコム、工場を狙うTSMC

(出所:Wall Street Journal)
ある報道機関は、インテル・ファウンドリーを軸にした合弁事業(JV)が今後10年間でどのように展開されるかについて、極めて詳細なロードマップを示しています。その内容についてはこちらをご覧ください。

(出所:SiliconANGLE Media Inc.)
この意見記事には一部同意できる点もありますが、TSMCがこのJVに関与するという想定は、極めて可能性が低いと考えます。さらに、米国のハイパースケーラー各社が、インテル・ファウンドリーをスピンアウトした新たなJVを長期的に支援し、その成功に向けて前例のない協力体制を敷くという主張もあります。しかし、彼らがなぜそこまでの協力をするのでしょうか?
最後に、この記事で提示されているJVのロードマップには、2つの重要な事実が完全に無視されています。第一に、インテルはもはや自社の主要な工場を完全には所有していません。SCIP(半導体共同投資プログラム)契約のことを覚えていますか?下記の分析レポートにおいて、アポロとの最新の取引について詳細に解説しておりますので、インベストリンゴのプラットフォーム上より併せてご覧ください。


これらのSCIP契約は、現在インテルをめぐって噂されている動きと非常に密接に関係しています。私は、数か月前にゲルシンガー元CEOの突然の退任後にリリースした下記の分析レポートの中で、それらの契約がもたらす問題について指摘しています。


「しかし、ゲルシンガー氏が進めてきた施策を簡単に覆すことはできません。例えば、彼とCFOのデビッド・ジンスナー氏が推進したSCIPプログラムにより、外部投資家であるブルックフィールドとアポロの2社がインテルのプロジェクトに関与しています。」
「SCIP(Semiconductor Co-Investment Program)は、半導体業界における新たな資金調達モデルであり、製造施設の拡張を目的としています。このプログラムは、インテルの「スマートキャピタル」戦略の一環として、資本支出を効率的に管理しながら市場の機会に迅速に対応することを目指しています。ブルックフィールドはアリゾナ州で建設中の工場に、アポロはアイルランド・レイクスリップのFab 34にそれぞれ権利を持つことになります。」
私は当初から、これらのSCIP契約は非常に悪いアイデアだと感じていましたが、その懸念が現実のものとなりつつあります。アポロとブルックフィールドは慈善団体ではなく、利益を得るために投資を行いました。しかし、それが実現しておらず、2024年の年次報告書によると、すでにペナルティが発生し始めていることが明らかになっています。
「例えば、2024年第4四半期には、アイルランドのSCIPに関連するペナルティとして7億5,500万ドルの費用を計上しました。これは、短期的な生産能力の調整に伴い、当社が建設の遅延を決定したことに起因するものです。さらに、これらの契約は、アリゾナの拡張キャンパスやアイルランドのFab 34でのウェハ生産量が増加するにつれて、将来的にインテルに帰属する純利益(損失)および1株当たり利益(損失)に大きく、かつ増大する影響を与えると見込まれています。」
さらに、CHIPs法による補助金がもたらした問題もあります。これは、上述の以前の分析レポートでも指摘した点です。
「また、最近発表されたCHIPS法の助成金には非常に厳しい条件が含まれており、これにより米国商務省がIFSの地位や所有権の変更に関する決定に事実上介入できるようになっています。」
これらの要因(およびその他の要素)によって、インテル・ファウンドリーの状況は非常に複雑になっています。では、実際にインテルでは何が起こっているのでしょうか?本稿では同社の現状に関して詳しく掘り下げていきます!
インテル(INTC)の本当の問題とは?
まずは少し振り返り、インテル(INTC)の抱える問題を再確認しましょう。最も大きな課題の一つは、技術的な製造リーダーシップの喪失です。この点については、社内外を問わず広く認識されています。
現時点では、なぜこのような事態に至ったのかよりも、その影響がこれまで、そして今後どのように続いていくのかが重要です。具体的には、歴史的に低水準の粗利益率による大幅な収益性の低下と、現在のウェハ生産量の約30%をTSMCに外部委託せざるを得ない状況にあります。
「現在のインテル全体を見てみると、当社の製造の約30%を複数のパートナー企業に外部委託しています。これは現状では最大の割合ですが、今後ゼロになることはないでしょう。」
二つ目の問題は設計に関するものです。インテルは、AMD(AMD)が主導したチップレット・アプローチへの移行に完全に乗り遅れました。その結果、特にサーバー市場において、AMDに大きくシェアを奪われ、財務的にも深刻な影響を受けています。さらに、この判断ミスによって、アップル(AAPL)を顧客として失うことにもなりました。
こうした問題を解決するために、ゲルシンガー氏はCEOとして再び迎え入れられましたが、いずれの課題にも対応できませんでした。彼の退任直後に執筆した下記の分析レポートにおいて、その失敗の要因を詳しく解説しており、下記のように述べております。


「取締役会がIDM 2.0戦略、特に大規模な工場建設計画を承認した際、基本的な2つの問いを見落としていたように思われます。一つ目は「なぜこれほどまでに大規模な生産能力が必要なのか?」。二つ目は「それをどうやって資金調達するのか?」です。この2つの問いへの答えは至って明快でした。「いいえ、それほど多くの生産能力は必要ありません。そして、仮に必要だとしても、それを賄う資金はありません。」」
「半導体製造の成功への大きな野心に囚われていたのか、ゲルシンガーCEOは工場建設と人員採用に突き進む道を選びました。しかし、本来彼がすべきだったのはその逆の行動でした。2024年第2四半期の業績発表が大失敗に終わり、パニック状態で実施された厳しい人員削減は、もし彼が就任直後の数カ月間に行っていれば、ここまで深刻なものにはならなかったでしょう。」
「インテルが2021年初めに着手すべきだったのは、せいぜい1つの新工場建設だけでした。しかし、ゲルシンガー氏はアリゾナ州に2つ、オハイオ州に1つ、さらにドイツにもう1つの工場建設を決断しました。現在、TSMC(TSM)へのアウトソーシングの規模を考慮すると、インテルの工場はおそらく稼働率が50%にも満たないと推測されます。これらの新しい立派な工場は実際には必要なく、その建設費用はインテルの財政にとって、最悪のタイミングで大きな負担となっています。」
インテル(INTC)には次に何が起こるのか?
まず、ブロードコム(または他のファブレス企業)によるインテル(INTC)の設計部門買収の可能性について考えましょう。さまざまな課題を抱えているものの、インテルのプロダクト部門は事業継続が可能な状態にあります。特にクライアント部門は、AMDに追いつき、市場シェアの減少を食い止めるという点で、一定の成果を上げています。確かに「Lunar Lake」は大きな失敗でしたが、そこから学びを得ています。
一方で、データセンター部門の状況ははるかに厳しいものです。AMDは依然としてサーバー市場で少なくとも2年のリードを保っており、その差を埋めるには、極めて集中した取り組み、大胆な戦略、そしてかなりの運が必要です。さらに、Gaudiの失敗も見逃せません。もしインテルがAMDの「Instinct」プラットフォームのような製品を開発できていたら、私も今このレポートを執筆していなかったかもしれません。
いずれにせよ、インテルのプロダクト部門が生き残る唯一の方法は、インテル・ファウンドリー(IFS)から完全に切り離され、TSMCに全面的に依存することだと考えています。IFSが再建されるまで、あるいは仮に再建が可能だとしても、それまではTSMCを頼る必要があります。では、ブロードコムや他社に売却される可能性はあるのか?私は低いと考えます。なぜなら、インテルにとって、プロダクト部門を維持することが、企業の象徴的なブランドを存続させる最も確実な選択肢だからです。設計上の問題は、プロセス技術のリーダーシップを取り戻すことと比べれば、相対的に解決が容易です。そのため、プロダクト部門は引き続きインテルの傘下にとどまると考えます。
一方で、インテル・ファウンドリーはすでに売却の準備が進められている状況です。ここ2年間、財務の分離、ERPやMRPシステムの独立、さらには子会社化といったステップを踏んでおり、その基盤はすでに整っているように見えます。
では、どのようにこの分離を実現するのか? 私の見立てでは、IFSはスピンアウトされ、非公開企業として再編される可能性が高いでしょう。ただし、SCIP契約やCHIPs法による所有権変更の制約が絡み、このプロセスは極めて複雑になります。実現は可能ですが、相当な時間を要するでしょう。資金調達に関しては、米国内には出資を希望する企業が多く存在し、中東地域でも有力な投資家が名乗りを上げる可能性が高いと考えます。
TSMC(TSM)がインテル(INTC)のIFSに関与する可能性は極めて低い?
TSMCがインテル・ファウンドリー・サービス(IFS)に関与する可能性は、以下の理由から極めて低いと考えられます。
1️⃣ TSMCは、インテルの工場に興味がないと明言している
TSMCはこれまでに2回、公の場でインテルの工場に関心がないと発言しています。
2️⃣ TSMCは、ファウンドリー市場における独占の印象を払拭しようとしている
TSMCは現在、ファウンドリー市場での独占企業と見なされることを回避するため、「Foundry 2.0」戦略を進めています。そのため、さらなる独占懸念を招くような動きを避けるはずです。仮にTSMCがインテルの工場を取得しようとすれば、独占禁止法の規制がその動きを阻止する可能性が高いでしょう。
3️⃣ TSMCは顧客と競争しない
これはTSMCの企業文化に深く根付いた原則です。TSMCは顧客と競争することはなく、それは企業買収についても同様だと考えられます。
4️⃣ TSMCは自社の拡張計画で手いっぱい
TSMCは現在、アメリカ、日本、ヨーロッパと、これまでにない規模の拡張計画を進めています。そのため、インテルの工場取得にまで手を広げる余裕はないでしょう。
もう一つ、TSMCがIFSを支援する可能性を考える際に考慮すべき点があります。それは、インテル(INTC)が一貫して「18Aプロセスは順調に進んでいる」と主張していることです。
インテルはこれまで、一度も「18Aが計画通りに進んでいない」と示唆したことがありません。しかし、私個人としては18Aが成功しないと考えており、その理由については何度も説明してきました(詳細は直近執筆した下記の分析レポートはご覧ください)。


しかし、インテルの18Aに関する主張は一貫しており、「計画通り進んでいる」との立場を崩していません。では、なぜTSMCの「支援」が必要なのでしょうか? もし本当に支援が必要だとすれば、インテルはこれまで嘘をついてきたことになります。しかし、現時点でそれを認めるとは考えにくいでしょう。
私個人の意見としては、インテルが嘘をついているとは思いません。18Aは理論上は非常に優れたプロセスであり、初期の欠陥密度も妥当な範囲に収まっているようです。しかし、真の課題は、大量生産へとスムーズに移行し、採算の取れる利益率を確保することにあります。インテルはこれを、14nmプロセス以降、長年にわたり成功させていません。
TSMCに関するもう一つの噂として、米国政府との間で、関税を巡る取引を交わすのではないかという見方があります。しかし、私はこの説を信じていません。仮に米国政府が台湾から輸入される半導体に関税を課した場合、それを負担するのは誰でしょうか?TSMCは台湾から直接チップを輸出しているわけではなく、輸出するのはTSMCの顧客です。そう考えれば、本来関税を負担すべきなのはTSMCではなく、その顧客企業のはずです。私は関税の専門家ではありませんが、個人的な見解としてはそのように考えています。
TSMCが米国政府と何らかの協議を行っている可能性は高いと思います。しかし、その内容はTSMCの米国での投資計画に関するものではないでしょうか。例えば、より高度なパッケージング技術の導入や、第3工場の建設スケジュールの前倒し、さらには第4工場の建設といった話が議論されている可能性があります。これらは合理的な展開ですが、TSMCがIFSに関与するというのは、現実的ではないと考えます。
インテル(INTC)に対する結論
現在、インテルの本社(サンタクララのロバート・ノイス・ビル)では何らかの動きが進行していると見られますが、それ自体は驚くことではありません。同社は存続の危機に直面しており、現在は正式なCEOも不在の状態です。しかし、巷で噂されている内容の多くは、現実的とは言えず、少なくとも実現の可能性は低いでしょう。
現実的な選択肢として、インテルの象徴的なブランドを存続させるためには、現在のプロダクト部門を維持しながら、IFSを切り離すことが最善策であるように見えます。ただし、IFSのスピンアウトと非公開化は非常に複雑で時間のかかるプロセスになるでしょう。しかし、この手続きが弁護士たちにとっては実に利益をもたらすものであることは間違いありません。
インテルの元同僚の皆さんの健闘を祈ります!
私は半導体&テクノロジー銘柄に関するレポートを毎週複数執筆しており、私のプロフィール上にてフォローをしていただくと、最新のレポートがリリースされる度にリアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることができます。
さらに、その他のアナリストも詳細な分析レポートを日々執筆しており、インベストリンゴのプラットフォーム上では「毎月約100件、年間で1000件以上」のレポートを提供しております。
そのため、私の半導体&テクノロジー銘柄に関する最新レポートを見逃さないために、是非、フォローしていただければと思います!
加えて、直近ではインテル(INTC)やASMLホールディング(ASML)といった他の半導体銘柄の最新の決算分析に関しても下記の詳細な分析レポートを執筆しておりますので、半導体株投資家の方は是非併せてご覧ください。
インテル(INTC)


ASMLホールディング(ASML)


アナリスト紹介:ウィリアム・キーティング
📍半導体&テクノロジー担当
.1740360393831.jpg)
キーティング氏のその他の半導体&テクノロジー銘柄のレポートに関心がございましたら、こちらのリンクより、キーティング氏のプロフィールページにてご覧いただければと思います。

インベストリンゴでは、弊社のアナリストが「高配当銘柄」から「AIや半導体関連のテクノロジー銘柄」まで、米国株個別企業に関する分析を日々日本語でアップデートしております。さらに、インベストリンゴのレポート上でカバーされている米国、及び、外国企業数は「250銘柄以上」(対象銘柄リストはこちら)となっております。米国株式市場に関心のある方は、是非、弊社プラットフォームより詳細な分析レポートをご覧いただければと思います。