インテル(INTC)の凋落の原因とは?新CEOリップ・ブー・タン氏が企業文化改革の重要性を強調!
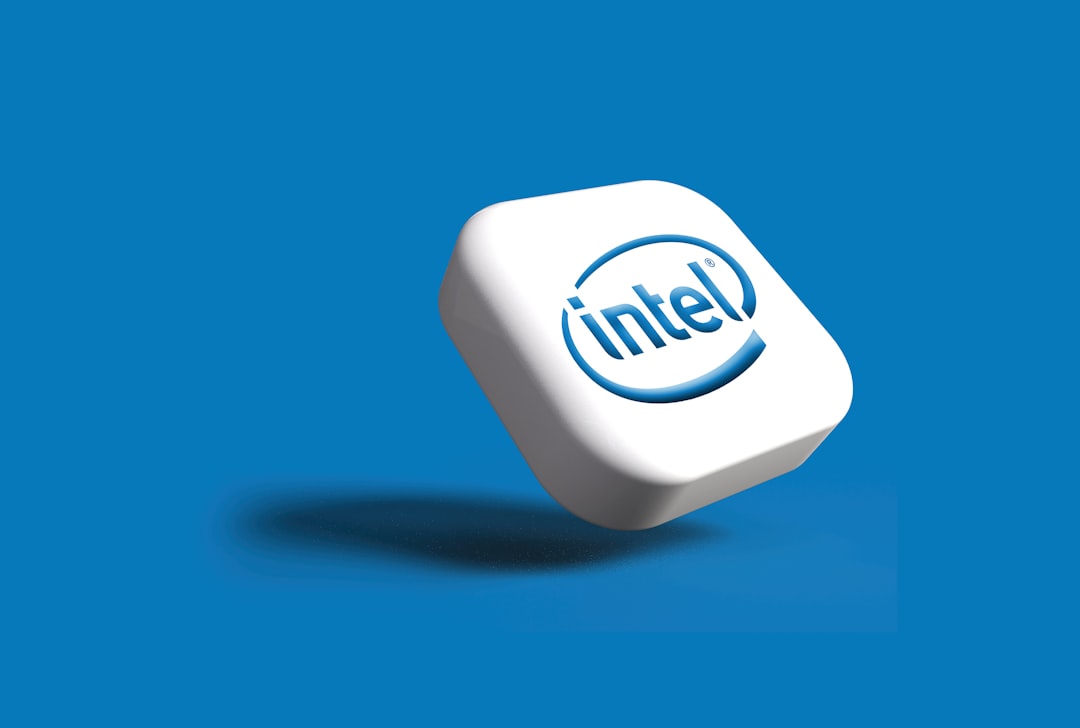
 ウィリアム・ キーティング
ウィリアム・ キーティング- 本稿では、注目の米国半導体関連銘柄である「インテル(INTC:Intel)の凋落の原因とは?」という疑問に答えるべく、新CEOのリップ・ブー・タン氏の最新の基調講演の詳細な分析を通じて、同社の将来性を詳しく解説していきます。
- インテル新CEOのリップ・ブー・タン氏は、顧客との信頼構築や優秀な人材の確保を最優先課題として掲げ、インテルの再建に向けた強い決意を語りました。
- タン氏は自身の経歴や半導体投資の実績、企業文化改革の重要性に触れ、イノベーションと効率性を両立する組織づくりを目指す姿勢を示しました。
- 具体的な数値目標やスケジュールの提示はありませんでしたが、インテルの課題を率直に認め、改善には時間がかかるとの認識を強調していました。
インテル(INTC:Intel)の凋落の理由とは?
インテル(INTC)の新CEOリップ・ブー・タン氏が、同社が開催する2日間にわたる招待制イベント「Intel Vision」の開会基調講演を行いました(詳細はこちらをご覧ください)。また、4月1日には、ミシェル・ジョンストン・ホルツハウス(MJ)氏が、「Intel Products Update & GTM」と題された別の基調講演を行っています。

やや興味深いことに、彼女の基調講演は以下のように紹介されています(詳細はこちらをご覧ください):
「インテル プロダクト グループのCEOであるミシェル・ジョンストン・ホルツハウス氏、チーフ・コマーシャル・オフィサーのクリストフ・シェル氏、そしてゲストたちが、私たちの未来を形作る技術、ソリューション、そして可能性について語ります。」
つまり、インテル・ファウンドリーは、インテル・プロダクツと同じように最上位の基調講演として扱われていないということです。興味深いですね。その代わりに、インテル・ファウンドリーについては、MJ氏の基調講演の中で取り上げられるようです。次の図が示すように、彼女のゲストの一人であるケビン・オバックリー氏が登壇することから、それがうかがえます。

そして、今回の2日間のイベントのラインナップの中にCFOであるデイビッド・ジンスナー氏の名前がないことが、ひときわ目を引きます。彼は最近までMJ氏とともにゲルシンガー氏の「退任」後の暫定共同CEOを務めていました。彼のインテルにおける今後の立場について、何を意味しているのでしょうか。ともあれ、インテルの新しいCEOとして2週間が経過した今、タン氏はインテルの未来についてどのようなビジョンを語ったのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
🚀お気に入りのアナリストをフォローして最新レポートをリアルタイムでGET🚀
ウィリアム・キーティング氏は半導体&テクノロジー銘柄に関するレポートを毎週複数執筆しており、プロフィール上にてフォローをしていただくと、最新のレポートがリリースされる度にリアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることができます。
さらに、その他のアナリストも詳細な分析レポートを日々執筆しており、インベストリンゴのプラットフォーム上では「毎月約100件、年間で1000件以上」のレポートを提供しております。
そのため、キーティング氏の半導体&テクノロジー銘柄に関する最新レポートに関心がございましたら、是非、フォローしていただければと思います!
タン氏は自身の基調講演を、スポンサー企業への感謝の言葉から始めました。彼は、彼らの出席と支援に対して感謝の意を表しました。では、そのスポンサー企業とは誰だったのでしょうか?

アクセンチュアやデロイトがこのイベントをスポンサーしている理由を理解するのは、正直言って非常に難しいです。さらにIBMとRed Hatの両社?そして最後にスーパーマイクロです。肝心の顧客であるPC OEM企業やハイパースケーラー企業などはどうしたのでしょうか?全く登場していません。本当に不思議です。
いずれにしても、タン氏は、自身が新たな役職についてからまだ14日しか経っていないものの、すでにいくつかの「明確な見解」があると述べています。以下に、その発言の一部をご紹介します。
「最優先事項は、顧客と時間を過ごすことです。」
「信頼できる関係や友情を築きたいと考えています。」
「謙虚な姿勢でこの役割に臨み、すべての分野から率直なフィードバックを求めています。」
「これから多くの努力が必要であり、私たちが期待に応えられていない分野も数多くあります。」
「強力なチームを結成し、信頼を得ることから始めていきます。」
彼はこのセグメントの締めくくりとして、インテルCEOとしての任期中に繰り返し語られることになりそうな言葉を述べています。
「私は、過度な期待を抱かせず、期待以上の成果を出すことを目指します。皆さまに心からご満足いただけるまでは、決して現状に満足することはありません。」
タン氏は、社内のエンジニアやアーキテクトたちとの対話に力を入れていることについて多く語り、優秀な人材の確保と採用が自身にとって最も重要な優先事項であると述べました。
「自らエンジニアやアーキテクトに積極的に声をかけていきます。」
「最優先事項は、優秀な人材の維持と新たな採用です。」
「インテルはこれまでの数年間で、一部の優秀な人材を失ってきました。」
「イノベーションと自律性を重んじる企業文化を築いていきたいと考えています。」
彼はまた、こうした人々とつながるために、組織の複数の階層にまで自ら進んで関わっていく意向があることも示しました。
次に、彼は自身の経歴について、かなりの時間をかけて説明しました。
「経歴としては、マレーシアで生まれ、シンガポールへ移り住みました。量子物理学を学び、その後アメリカに渡り、大学院では原子力工学の学位を取得しました。非常に興味深い経歴です。スリーマイル島の事故の後、博士課程は修了しませんでしたが、シリコンバレーに魅了されました。そして、300万ドルを元手にウォルデンを創業し、50億ドル規模にまで成長させました。」
その後、彼は自身のベンチャーキャピタル会社「ウォルデン」の社名の由来について、私がこれまで知らなかった興味深いエピソードを共有してくれました。
「思想家・哲学者であるヘンリー・デイヴィッド・ソローにインスピレーションを受けました。愛でも、お金でも、名声でもなく、「真実を与えてほしい」という考え方です。真実があれば、問題を解決し、チームとして前進することができます。」

「私が彼を尊敬するのは、彼が逆張りの思考を持つ人物であり、優れた職人でもあったからです。」
ソローは1854年に自身の著書『ウォールデン』を出版しました。詳細はこちらをご覧ください。
「ソローの『ウォールデン』は、「孤独の実践」とも言える作品です。この本の元のタイトルは『ウォールデン、または森の生活』であり、ソローが友人であり、同じ超越主義の作家でもあったラルフ・ワルド・エマーソンの所有地にある小屋で過ごした2年間の生活を記録したものです。その小屋は、ウォールデン池と呼ばれる湖の近くにありました。」
次にタン氏は、自身が半導体分野に投資する際に取った逆張りのアプローチについて語りました。当時、シリコンバレーの他のベンチャーキャピタル企業は、半導体業界を「斜陽産業」と見なしていたことにも触れています。
「ベンチャーキャピタリストとして、私は半導体分野に多くの投資を行ってきましたが、他のVCたちはこの分野に関心を示しませんでした。「斜陽産業」と見なされていたのです。これまでに私は251件の半導体投資を行い、43社のIPOを実現させ、25件のM&Aを成功させてきました。」
前述のとおり、謙虚さについて多く語る人物である一方で、自身の実績について話すときにはその謙虚さが影をひそめるようです。続いて、彼はケイデンス(CDNS)社のCEOとしての時期について語ります。
「ケイデンス社では12年間にわたりCEOを務めました。その間にチームの文化を改革し、顧客との深いパートナーシップを築きました。さらに、DenaliやNew Semiなど、複数の企業買収も行いました。これらはすべて、システム設計の実現を可能にする取り組みであり、同社を一桁成長から二桁成長へと変革させました。毎年12~14の新製品を自社開発で生み出し、対応可能な市場規模を3倍に拡大しました。株価は3,200%上昇しました。」
ここでもまた、あの深い謙虚さがにじみ出ていますね :-) 最後に、自身の経歴を締めくくる形で、インテルの取締役会(BoD)での2年間の経験についても言及しています。
「インテルの取締役会に2年間在籍し、多くのことを学びました。この経験は、現在の役割を担ううえで非常に良い準備になったと感じています。インテルは象徴的で不可欠な企業であり、業界全体、そしてアメリカにとっても非常に重要な存在です。インテルでは多くのメンターに出会い、大きな刺激を受けました。ショーン・マローニ氏、アルバート・ユー氏、ダディ・パールマター氏などがその代表です。」

彼がキャリアのこの段階でインテルのCEO職を引き受けた理由は何だったのでしょうか?
「なぜこの挑戦を引き受けたのか?それは、この会社を心から愛しているからです。これまで、この会社が苦しんでいる姿を見るのは、とてもつらいことでした。」
この点について、タン氏が長年インテルに対して抱いてきた敬意や憧れの気持ちは、本当に心からのものだと感じられます。続けて、彼はインテルが現在苦境にある理由についていくつかコメントを述べました。
「これは決して簡単なことではありません。私たちはイノベーションの面で後れを取り、変化への対応も遅すぎました。皆さまには、もっと良いものを提供するべきだと感じています。私たちは改善する必要がありますし、必ず改善していきます。厳しいフィードバックこそが最も価値あるものです。私は何をすべきかを正確に知りたいのです。私たちは、皆さまとの関わり方を根本的に見直し、単なるベンダーではなく、真のパートナーになります。」
彼は「カルチャー(企業文化)」という言葉を何度も口にし、それをよりイノベーションや効率性に重きを置いたものへと変えていく必要があると述べています。
「まずはカルチャーから始めます。カルチャーの変革を促進しなければなりません。イノベーションという本質的な要素に会社の焦点を再び当て、バランスシートや効率性にも注力していきます。」
「イノベーションはインキュベーション(育成)から始まります。インテルのような大企業においても、私は「初日のスタートアップ精神」を実践したいと考えています。新しいアイデアを歓迎し、社内から自由にイノベーションが生まれる環境を整えます。そして、人とアイデアの双方にしっかりとリソースを投入します。働き方をシンプルにし、官僚主義を排除します。官僚主義はイノベーションを阻害します。私はそれを理想の形に仕上げ、チーム全体に広がる可能性を解き放ちます。そして、外部からも新たな優秀な人材を引き寄せていきます。」
これは、私が最近書いたインテルにおける彼の最大の課題に関する内容と非常によく一致しています(詳細はインベストリンゴのプラットフォーム上にてご覧ください)。


タン氏は、AIによるアーキテクチャの変革、量子コンピューティングやヒューマノイドロボットへの関心、そしてカスタムシリコンがインテルの将来において重要な役割を果たすべきだという見解などに簡単に触れた後、インテルの2つの主要な製品グループについてごく簡潔に振り返りました。
「クライアント・コンピューティング分野では、強力なイノベーションを推進していく必要があります。今年後半には18Aプロセスによる「Panther Lake」が登場予定です。AIエッジの実現にも取り組みます。」
「データセンター分野では、提供価値の強化が必要です。多くの優秀な人材を失っており、採用を進めなければなりません。より高い性能と効率性が求められており、AI推論においても大きな役割を果たす必要があります。AI全般の分野については、現時点での当社の立ち位置に満足していません。ここで新たなページをめくり、過去の失敗から得た教訓を正しく活かしていきます。ただし、それは一朝一夕で実現するものではありません。」
また、インテル・ファウンドリーについても、以下のとおりやや詳しく説明しました。
「優れたファウンドリーを築くことにも、同じように全力で取り組んでいます。柔軟で、強靭かつ安全なサプライチェーンが必要です。チームリーダーたちから毎週報告を受けており、進捗は随時皆さまにもお伝えしていきます。求められる基準は非常に高いです。現状を正確に把握し、これから進むべき明確な道筋を定めなければなりません。信頼が何より重要です。」
「お客様それぞれに独自のアプローチがあり、私たちは学び、適応する必要があります。すべてのお客様には、それぞれの好みがあります。どのEDAプレーヤーを使っているのか、どのIPを使っているのか──私はこのエコシステムを熟知しています。」
「18Aプロセスの進展も続けています。2025年下半期には「Panther Lake」によって大量生産を予定しており、初の外部テープアウトも控えています。歩留まり、品質、カスタマーサービスの向上を推進していく必要がありますが、時間はかかります。私は忍耐強く取り組みます。必要なのは2~3社の主要顧客です。ファウンドリーに関するさらなる情報は、4月末に開催される「Direct Connect」イベントでお話しします。インテルはエンジニアリング主導の企業になります。」
インテルでこれまでと違う取り組みを進めたいという点について、彼は3つの戦略を示しました。ソフトウェア優先の設計アプローチ、AI主導のシステム設計アプローチ、そして目的に特化した(カスタム)シリコンの採用です。

ただし、この部分の基調講演にはあまり具体的な内容が含まれておらず、個人的にはこのセグメントが最も弱かったと感じました。最初の2つのポイントはかなり一般的ですし、3つ目に関しては正直少し混乱しました。すべてのシリコンはそもそも目的に応じて設計されているのではないでしょうか?正直よく理解できませんでした。
まとめ
予想どおり、今回の就任後初となる基調講演では、タン氏がインテル再建に向けてどのような戦略を描いているのか、深い洞察を得ることはできませんでした。その代わりに示されたのは、同社が抱える多くの課題を率直に認める姿勢、顧客から真実を学ぼうとする熱意、そして優秀な人材の確保と採用への強いコミットメントでした。
彼は何度か、同社のバランスシートを立て直す必要があると述べており、これは今後実施されるコスト削減や人員削減の前触れではないかと感じられました。全体を通して、具体的な数値目標やタイムラインには一切触れず、改善には時間がかかるものであり、一夜にして実現するものではないと、繰り返し強調していました。
講演の最後には、自らに対して「インテルにどれくらいの期間在籍するつもりか?」という修辞的な問いを投げかけました。その答えは──
「必要な限り、ここにいます」
さて、インテルは今後どうなるでしょうか。今後の展開に関しても、引き続き、レポートの執筆を通じて皆様に共有していきますので、お見逃しなく!
🚀お気に入りのアナリストをフォローして最新レポートをリアルタイムでGET🚀

ウィリアム・キーティング氏は半導体&テクノロジー銘柄に関するレポートを毎週複数執筆しており、プロフィール上にてフォローをしていただくと、最新のレポートがリリースされる度にリアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることができます。
さらに、その他のアナリストも詳細な分析レポートを日々執筆しており、インベストリンゴのプラットフォーム上では「毎月約100件、年間で1000件以上」のレポートを提供しております。
そのため、キーティング氏の半導体&テクノロジー銘柄に関する最新レポートに関心がございましたら、是非、フォローしていただければと思います!
さらに、その他のインテル(INTC)に関するレポートに関心がございましたら、こちらのリンクより、インテルのページにてご覧いただければと思います。

📢 知識は共有することでさらに価値を増します
✨ この情報が役立つと感じたら、ぜひ周囲の方とシェアをお願いいたします✨

アナリスト紹介:ウィリアム・キーティング
📍半導体&テクノロジー担当

キーティング氏のその他の半導体&テクノロジー銘柄のレポートに関心がございましたら、こちらのリンクより、キーティング氏のプロフィールページにてご覧いただければと思います。

インベストリンゴでは、弊社のアナリストが「高配当銘柄」から「AIや半導体関連のテクノロジー銘柄」まで、米国株個別企業に関する分析を日々日本語でアップデートしております。さらに、インベストリンゴのレポート上でカバーされている米国、及び、外国企業数は「250銘柄以上」(対象銘柄リストはこちら)となっております。米国株式市場に関心のある方は、是非、弊社プラットフォームより詳細な分析レポートをご覧いただければと思います。